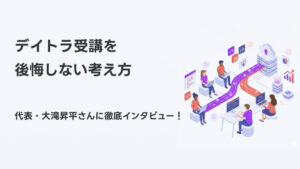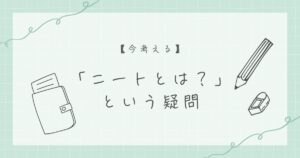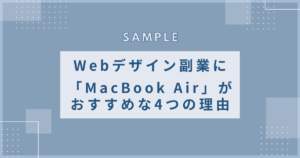【効率的な貯金の仕方】支出を減らし収入を増やすコツを伝授!
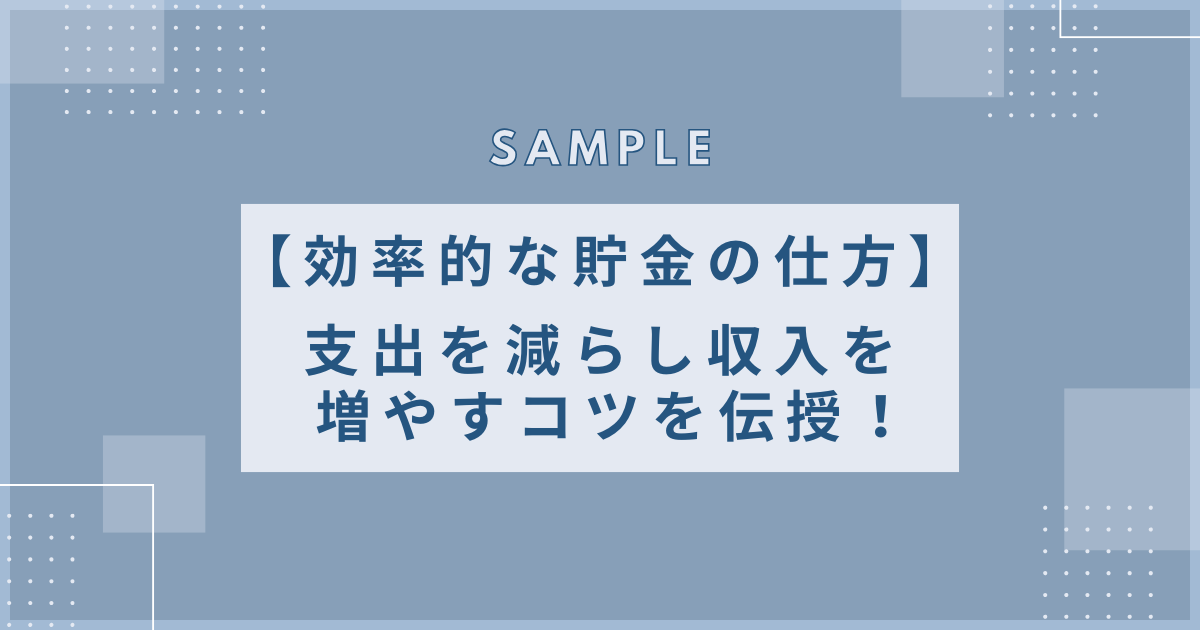
ライフスタイルの変化やイベントがあるたびに出ていってしまうのがお金。
しっかり貯金して備えておこうと思っても、
「貯金の仕方がわからない……」
「何をすれば貯金できるようになるの?」
といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
今回は「貯金の仕方のコツ」として、お金を貯めるためにすると良い行動をご紹介します。
貯金するための行動の参考になれば幸いです。
なお、着実に貯金を増やしていくにはNISAやiDeCo、投資信託といった制度を活用するのもおすすめです。楽天証券なら簡単に投資商品の購入や積立設定ができるので、ぜひ口座を作ってみてはいかがでしょうか。
やってしまうと「お金が貯まらない」行動3つ
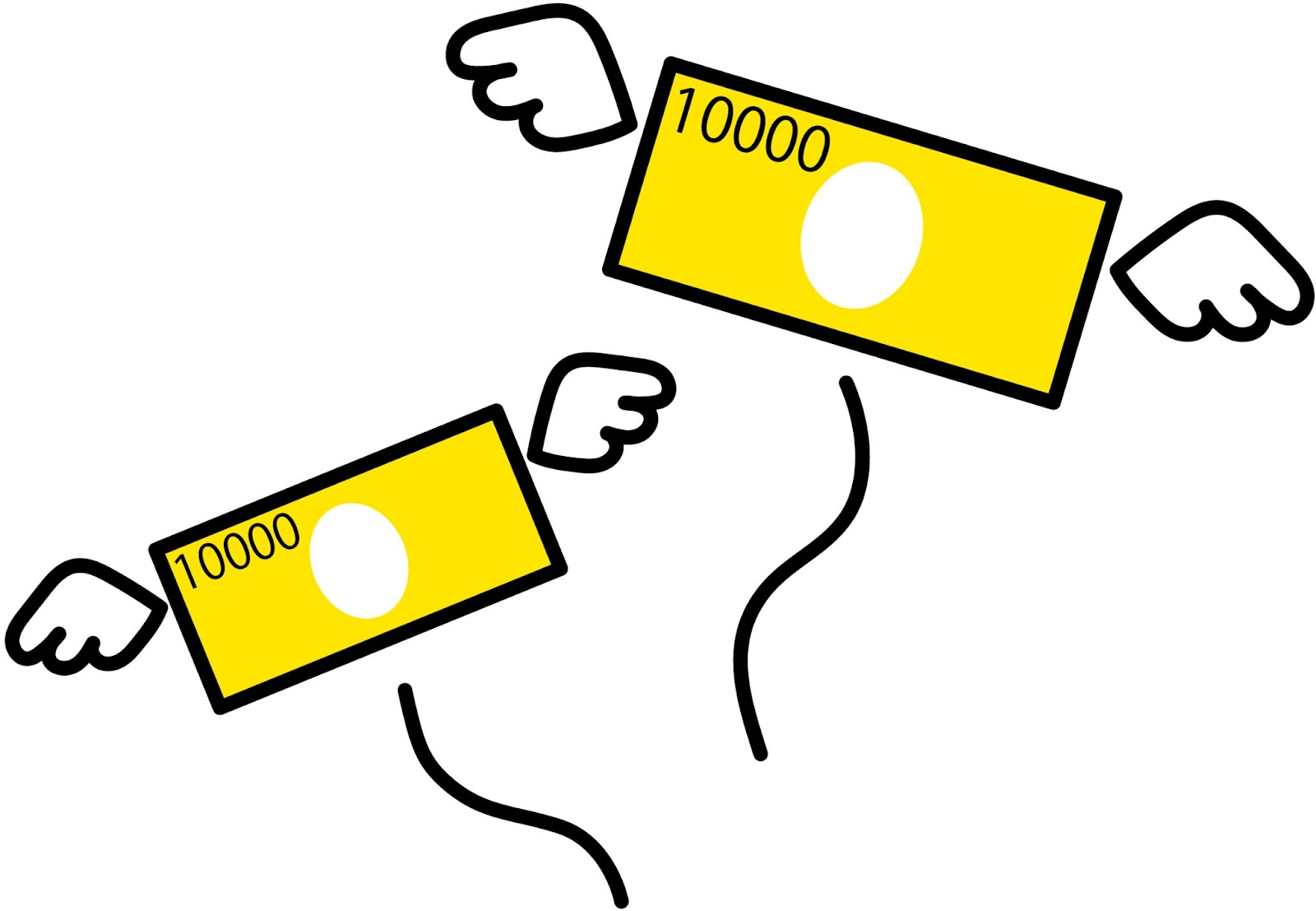
やってしまうと「お金が貯まらない」行動は次の3つです。
- 家計の収支を把握せずにお金を使っている
- 衝動買いをしている
- 使った後に残ったお金を貯めようとしている
それぞれ解説します。
行動1. 家計の収支を把握せずにお金を使っている
自分の生活において、収入と支出の金額がどのくらいなのかを把握していない方は注意が必要です。
収入と支出の状況を把握しないと、どこにかかる支出が無駄なのかが明確になりません。
貯金する金額を捻出するためには、無駄に使っている、あるいは必要以上にかかっているお金を節約し、支出を浮かせることが重要です。
そのため、無駄を洗い出すためにも収支状況をわかっている必要があります。
行動2. 衝動買いをしている
衝動買いは「衝動」という言葉に現れている通り衝動的に、つまり何も考えず無計画に感情と反射のまま買い物をしてしまうことを指します。
せっかく家計の収支を把握して節約する部分や金額がわかったとしても、勢いで買い物をしてはせっかくの努力が水の泡です。
買い物をする前に「これは本当に今の自分にどうしても必要なものか」を考える癖をつけておくと良いでしょう。
行動3. 使った後に残ったお金を貯めようとしている
貯金するために何にいくらを使うか予算を立てたとき「今月はまだこれだけ使える」と思うのは少し危険です。
「今月はまだこれだけのお金が残っているから、もう少し使っても大丈夫」と思ってしまうと、「あとちょっとだけ使っても……」と支出が重なることがあります。
その結果、最終的に残った金額は雀の涙ほどだった、ということもありえるので、気をつけたいところです。
貯金を増やすために押さえておくべき「原理原則」3つ
貯金を増やすために押さえておくべき原理原則は、以下のとおりです。
- 目的、目標、締め切りを設定する
- お金が貯まる仕組みを知る
- 家計の収支を記録して現状を把握する
順番に説明していきます。
原理原則1. 目的、目標、締め切りを設定する
なんのために、いつまでに、いくら貯めるのかがはっきりわかっていないと貯金は難しいでしょう。目的もなくただ貯金しようとしても、モチベーションが上がらなかったり、無計画にお金を使ったりしてしまいます。
また、貯金の目的が明確ではないことのデメリットとして「毎月どのぐらい貯金すべきかわからない」ことも挙げられます。
月々の貯金額がわからないと、貯め方にムラができて「今月は貯金できなかった」という月ができることも……。
原理原則2. お金が貯まる仕組みを知る
貯金ができる状態とは「収入>支出」になっていることを指します。
この収支のバランスが支出にかたよってしまうと、入ってくるお金よりもでて行くお金が多くなり、お金が貯まらなくなります。
穴の空いたバケツに水を注いだところで穴から水が漏れ出てしまうのと同じです。
支出の無駄という穴を塞がないといつまでも水、つまりお金は口座というバケツに溜まっていきません。
支出を少なくし、入ってくるお金を増やすのが貯金をするための第一歩となります。
原理原則3. 家計の収支を記録して現状を把握する
自分の月々の給与を把握していない人は意外に多いかもしれません。
しかし、自分にいくらの収入があり、そこからいくら支出としてお金が出て行くかを知らないと、貯金計画は立てられません。まずは家計の収支を知るところから始めましょう。
対策としては、家計簿をつけることで、いくらのお金が入ってきていくらのお金が出て行くのかがわかるようになります。
「家計簿をつけていると支出が多くてがっかりしてしまうし恥ずかしいからやりたくない」という方もいるかもしれません。著者も以前、家計簿に多すぎる支出を記載するのが嫌でした。
しかし、家計簿で支出が多いこと、あるいはどこの支出が無駄なのかを理解することは恥ずかしいことではありません。支出の記録は「支出対策」を立てるための準備だと考えると気持ちが変わりました。
家計簿は誰かに見せびらかすものではありませんから、正直に収入と支出を家計簿につけて見える化し、バケツの穴をふさいでいきましょう。
お金が貯まる貯金の仕方:支出を減らすコツ5つ
支出を減らすコツは、以下の5つです。
- 固定費を見直して浮いたお金を貯金する
- 先取り貯金をする
- 口座を用途別に分ける
- 無理な節約はしないようにする
- 浪費が心配な方は証券口座での積立を利用する
順番に解説していきます。
コツ1.固定費を見直して浮いたお金を貯金する
家賃や保険料、通信料などの固定費は、一度見直して安くすれば手を加えない限りずっと節約効果が続きます。
| 見直し項目 | 見直し内容 |
| 保険料 | 保証内容に無駄なものがないかを確認する |
| 家賃 | より安い物件に引っ越す、または値下げ交渉をする |
| サブスク | 使っていないサービスに料金を払っていないか確認する |
| 通信費 | 自分の端末の使い方に合った料金プランになっているか確認する |
特に保険は医療の進歩や時代の流れに合わせて内容を見直して、ご自身に見合った保証と保険料に変えていくことが大切です。
たとえば、今は手術を受けても入院はしないパターンが増えており、手厚すぎる入院保証をつけているのはお金の無駄になるケースもあります。
遺伝や体質などを考え無駄な保証を省くことで、保険料が安くなるケースもあるため、見直しは必須です。
コツ2.先取り貯金をする
貯金をする金額を先に引いておく「先取り貯金」をすることで、無駄な支出をカットすることができます。
先取り貯金で重要なのは、先取りしてよけたお金をなるべく手が入らないところに置いておくことです。
別口座を作って入金し、その口座のキャッシュカードと通帳は出すのが面倒なところにしまっておくだけでも、「ちょっとくらい使ってもいいかな……」という誘惑に負けにくくなります。
コツ3.口座を用途別に分ける
生活費用口座・貯蓄用口座・お小遣い用口座など、使うお金の用途ごとに口座を分けるのも良い方法です。
用途別に口座を分けておけば、何に使うための口座にいくらお金が入っているかわかりやすくなり、貯金額の管理がぐっと楽になります。月々の出費の流れが把握しやすくなるため、買い物計画が立てやすくなるのもメリットです。
また、金融機関への預金は預金保険制度で1000万円までならその利息と貯金額が保護されます。1000万円を超える場合は金融機関の破綻リスクにも備えるためにも口座を分けるとよいですね。
コツ4.無理な節約はしないようにする
あまりにも生活レベルが下がるような節約をしてしまうとストレスがかかり、反動で散財してしまうこともあります。
そういった事態を避けるためにも、あまり切り詰めすぎた節約はしないことがおすすめです。
食費を切り詰めすぎて栄養がかたよってしまったり、光熱費を下げようと冷暖房を我慢した結果病気になってしまったりすると、病院代や薬代がかかりかえって支出が増えることになります。
体と心に無理のない範囲で、「節約を楽しもう」くらいの気持ちの余裕を持って生活することが大切です。
コツ5.浪費が心配な人は証券口座での積立を利用する
後述しますが、NISAやiDeCo、投資信託などをしながら積立貯金ができる証券口座も、貯蓄用口座としておすすめです。
ただ毎月積立で貯金ができるだけではなく、比較的安定した投資の側面もあるため、運が良ければ預けていたお金が増える可能性もあります。
自動引き落としで決まった金額を積み立てることができるため、先取り貯金のために自分の手でお金をよけることに自信が持てない人は試してみるとよいでしょう。
お金が貯まる貯金の仕方:収入を増やすコツ4つ
収入を増やすコツは、以下の4つです。
- 資格を取る
- 副業する
- 転職する
- いろいろな制度や金融商品を活用する
こちらも解説していきます。
コツ1:資格を取る
会社によっては、特定の資格を取得すると資格手当がつき、収入がアップすることがあります。また、資格取得によってスキルアップし、任される仕事が増えたり役職に就いたりすると、給与が上がることもあります。
資格を取るにはそれなりの努力が必要ですが、資格学習代は未来への投資だと思ってしっかり学習しましょう。実力を裏付ける資格を取得できれば、後述する副業や転職にも役立つ場合があります。
コツ2:副業する
本業のスキルや資格、趣味のスキルなどを活かして副業をしてみるのも収入アップのひとつの手です。著者はWebスキルを学習してWebデザインやライティングの仕事をしています。
二足の草鞋を履いての生活は少し大変です。しかし、それ以上に得られる収入や日々貯まっていくへそくり貯金の額に思わず笑みが溢れることもあります。
副業は会社によっては禁止されていることもあるので、就業規則をしっかり守った上でやる・やらないの判断をするようにしましょう。
コツ3:転職する
現状よりも年収が高い企業に転職するのもいいでしょう。先述したように、資格やスキルを取得して身につけておけば、転職活動での自分の価値が上がっていきます。
終身雇用の時代が終わりを迎えつつある昨今、スキルをつけてより高い志や年収の会社に転職するのは珍しいことではありません。
年収が上がれば貯金できる額も増えますので、転職も視野に入れて考えてみるといいですね。
コツ4:いろいろな制度や金融商品を活用する
NISAやiDeCo、投資信託など、日本にはお金を貯めながら投資できる制度や金融商品が揃っています。
これらをうまく使い、貯金するだけでなく「投資して増やす」こともこれからの時代は重要です。
どれも積み立てでお金を貯められ、さらに自動引き落としの設定をしておけば先取り貯金のように使えます。
ただ、iDeCoは積み立てたお金を引き出せるようになるのが60歳からなので、その点は注意が必要です。
NISA、iDeCo、投資信託をするなら楽天証券がおすすめ
ここまでさまざまな貯金の仕方についてコツをご紹介してきました。中でもNISAやiDeCo、投資信託などを利用することは、お金を貯めるだけでなく増やせる可能性にもつながります。
著者もWeb系オンラインスクールの受講料をNISAで積み立てていたら5,000円ほど投資の利益がついて、その分で学習の事前知識を得るための本が買えました。
しかし、「NISAやiDeCo、投資信託をやってみたいけど、何をどうすればいいの?」とお思いの方もいるでしょう。
おすすめの方法は、楽天証券で証券口座を開設して活用することです。
楽天証券は幅広い金融商品ラインナップで、投資の初心者からベテランまで満足できる品揃えをしています。
また、楽天ポイントを連携させることによって投資するたびにポイントが貯まったり、そのポイントをさらに投資したりすることが可能です。
手数料も業界最安値の水準で、かけたお金を現金化する際に必要以上のお金はかかりません。
口座開設もメールアドレスがあればPCでもスマホでも簡単に行うことができます。
口座開設と同時にNISA等が始められるスピーディーな面も魅力です。
楽天会員のアカウントがあれば、さらに簡単に口座開設ができます。
口座開設は無料です。「もしかしたら証券口座を使うかも」という段階でもあらかじめ口座開設をしておけば後からの手間がなくなります。
よくある質問
貯金の仕方について多くの人が気にする質問を3つ挙げました。参考になれば幸いです。
Q:貯金の仕方のコツで一番楽なのはどれですか?
A:自動積立で行う貯金は、一度手続きをしておくと解約手続きをしない限りずっと貯金し続けてくれるので、最初の手間だけですみます。
Q:家計簿はどうやってつければいいですか?
A:人によってつけ方は異なりますが、家計簿をつける目的は「いくら収入がある中で、何にどのぐらいの支出をしているか」を理解して収支の内容を改めることです。
紙の家計簿、家計簿アプリ、表計算ソフトの家計簿テンプレートなど、いくつか試したうえで家計簿をつける目的を果たせるものを選ぶのが良いでしょう。
Q:子育てにかかるお金がいくらか教えてください。
A:子供が生まれてから大学を卒業するまでにかかる金額は約2,000万円〜3,000万円と言われていますが、この金額を超えることもあります。
これは私立の学校に通うか公立の学校に通うかによっても違いが出ますが、ライフステージの変化によってお金がかかるのは間違いない事実です。
ライフステージの変化が訪れる前から貯金しておきましょう。
まとめ
貯金の原理原則と支出・収入のコツをご紹介してきました。
貯金の仕方のコツは、以下の通りです。
- お金がたまらない行動をとらない
- 貯金の原理原則を押さえる
- 支出を減らす
- 収入を増やす
- 国のいろいろな制度や金融商品を活用する
この記事でご紹介した行動を実際に行うことによって初めて「お金が貯まっていく」状態が実現します。
支出を減らす・収入を増やすコツにひとつでもチャレンジすれば貯金も貯まりやすいと思うので、ぜひみなさんも実践してみてください!
NISAやiDeCo、投資信託などの制度を利用した貯金は、楽天証券の口座を使うのがおすすめです。
これを機に口座開設をして、今日からさっそく積立生活を始めてみませんか?